目次
プレイングマネジャー の悩み
なぜ プレイングマネジャー はプレイしてしまうのか? うつべき手段 まとめ
1. プレイングマネジャー の悩み1)今や約9割が プレイングマネジャー という実態
現代の企業組織において「 プレイングマネジャー (プレイヤーとマネジャーを兼任する管理職)」は、もはや当たり前と言ってよい存在です。産業能率大学が実施した「上場企業の課長に関する実態調査」 によると、上場企業の課長の実に98.5%が プレイングマネジャー であり、加重平均の算出ではプレイング業務は49.1%に達しています。この調査では、プレイヤーとしての役割が全くない課長はわずか1.5%しかおらず、ほとんどの課長がプレイヤー業務とマネジメント業務を両方担っていることが明らかになりました。
また、リクルートワークス研究所の調査でも同様の傾向が見られており、87.3%のマネジャーがプレイング業務を行っていると回答しています。さらに驚くべきことに、約3割のマネジャーがプレイング業務に自身の仕事時間の50%以上を費やしている実態が浮き彫りになりました。
2)管理職が抱える現実とその先にある課題
管理職に昇進すると、これまでのように自分の業務だけに集中するわけにはいきません。プレイヤーとしての実務に加えて、部下の育成やチーム全体のマネジメント、さらに部署全体の目標達成に責任を持つことになります。加えて、経営層からは、成果や言動に対するプレッシャーはこれまで以上に大きくなります。
多くの管理職はこうした「責任の重さ」や「業務量の多さ」の中で、日常的に多忙で余裕のない状態にあるため、部下の支援や組織運営に手をかけたくても、自分の業務で手一杯になってしまう管理職も少なくありません。
また、時間的な拘束も見逃せないポイントです。管理職になると業務の幅が広がる分、働く時間も長くなりがちです。しかし、その分の報酬が見合っているとは限らず、むしろ報酬面での“逆転現象”が生じることもあります。役職手当が支給される代わりに、残業代がカットされる企業も多く、業務量が多すぎると、手当が実質的に割に合わないというケースが見られます。
このように、「責任は増えるのに報酬はあまり変わらない」「業務量は増すのに見返りが少ない」という実態があると、管理職自身のモチベーションが下がりやすくなります。また、そうした現状を見た若手社員は「管理職になりたくない」と感じるのも自然な流れです。その結果として、管理職候補が育たず、今いる管理職に業務と責任が一層集中するという、悪循環が生まれています。
深刻なのは、「人材不足」と「自分の業務量の増加」が、同時進行で管理職を追い込んでいる点です。この二つの要因が大きな負担となり、現場をさらに疲弊させる構造が続いています。
3)管理職になりたい人が減少している
出典:パーソルホールディングス株式会社 管理職になりたくない社員がなぜ増えるのか|原因と対策を解説 より さらに深刻な問題として、管理職を目指したいと考える社員が減少していることが挙げられます。パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査 2024」によると、「現在の会社で管理職になりたい」と回答した人はわずか17.2%で、2021年の調査から6.8ポイント下降しています。
特に20代の若手社員では、管理職を希望する割合が2021年の36.4%から2024年には28.2%と大きく低下しています。また性別で見ると、「管理職になりたい」と回答した人は男性で20.4%、女性で12.3%と、女性の管理職志向が特に低いことも明らかになっています。
こうした状況も影響し、企業は「自分の後任を担える人材・次世代リーダーが育っていない」という深刻な人事課題に直面しています。リクルートマネジメントソリューションズの「人事・組織戦略における課題調査」では、この課題が最も多く挙げられており、特に経営層が抱える大きな問題となっています。
2. なぜ プレイングマネジャー はプレイしてしまうのか?1)構造的に プレイングマネジャー が自ら仕事を抱えてしまう理由 プレイングマネジャー が自ら仕事を抱えてしまうのには、いくつかの構造的な要因があります。リクルートワークス研究所の調査によると、プレイング業務を行う主な理由として以下が挙げられています。
1. 業務量が多く、自分もプレイヤーとして加わる必要がある (57.3%)
これらの結果から、マネジャーが責任を持つ現場の厳しい実態が浮かび上がってきます。チームとして達成すべき業績目標やミッションを成し遂げるためには、以前よりも高度かつ大量の業務をスピーディに処理する必要がある一方で、人手不足の環境下で十分なスキルを持った部下を確保するのは困難です。さらに、働き方改革の影響もあり、部下の超過労働を減らすためにマネジャー自身が業務を抱え込む傾向も見られます。
2)構造的要因の本質 実際には、 プレイングマネジャー が自ら業務を抱え込む本質的な要因として、以下の3つが考えられます。
① 役割肥大化:成果と育成両方に責任 マネジャーには、部門の業績達成という「成果への責任」と、部下の育成・成長という「育成への責任」の両方が課せられています。これらの役割は時に相反する側面を持ち、日々の業務において両立させることは極めて困難です。そして経営からの圧力は常に「成果への責任」のほうが高く、目先の目標達成のために、プレイヤーとしての能力が高い自らが行動して数字を達成することとなります。
② リソースの不足(人材/予算)
多くの組織では、適切な人材や予算のリソースが不足しています。特に少子高齢化、労働人口の減少といった社会的背景の中で、十分なリソースを確保することが難しくなっており、マネジャー自身が現場で手を動かさざるを得ない状況が生じています。特に最近では、企業の「ホワイト化」が進み、特に若手の離職を意識すると残業を頼むこともできず、残業代が発生しないマネジャーが時間を使い、自ら業務を処理するというケースも生まれています。
③ スキルとマインドのギャップ
多くのプレイングマネジャーは、優秀なプレイヤーとしての実績を買われて昇進したケースが多く、マネジメントスキルやマインドセットの面でギャップを感じていることも少なくありません。つまり部下のプレイヤーとしての能力に不満を覚えるケースが多くあります。特に「信頼して任せる」というマインドセットへの転換が難しいことが、プレイング業務の比率を高くする一因となっています。
3)プレイとマネージの最適なバランスとは リクルートワークス研究所の調査によると、プレイング業務比率が40%を超えると業績が落ちる傾向にあることが明らかになっています。
出典:リクルートワークス研究所 Works Report 2020「プレイングマネジャーの時代」より 具体的には、プレイング業務の割合とチーム成果の関係を分析した結果、プレイング業務をまったく行わないマネジャーのチーム成果指標の平均値が3.08であるのに対し、プレイング業務の割合が「20%~30%未満」のマネジャーのチーム成果指標は3.27と最も高くなっています。一方、プレイング業務の割合が増えるにつれて、チーム成果指標は徐々に低下し、「80%以上」のマネジャーでは2.86と最低値を示しています。
これらの結果から、目指すべきプレイとマネージのバランスとして、以下の3つのポイントが重要と言えます。
①プレイングの比率を30%以下にする
プレイング業務の割合を30%以下に抑えることで、マネジメント業務に十分な時間を確保し、チーム全体の成果を最大化することができます。
②プレイングする仕事の中身を吟味する
マネジャーがプレイヤーとして関わる業務は、戦略的に選ぶことが重要です。特に改善レベル、変革レベルの仕事など、知識と経験が必要で、ネットワークを活用して変化を起こすことが求められるような高度な業務には、マネジャー自身が関わることでチーム成果にプラスを与えることができます。また、誰もやったことがない新しい業務、定型的なものがなにもない業務なども、経験と知識を必要とするため、若手に任せることが必ずしも良い結果を生まないケースがあります。さらに上長を巻き込んだ業務の場合は、中間管理職であるマネジャーが積極的にかかわることで組織としての推進力となることが期待できます。
③プレイングしながら業務改善と部下の教育を行う
プレイング業務を行う際には、単にタスクをこなすだけでなく、常にマネジャーとしての視点を持ち、それを部下の育成や業務改善に活かすことが重要です。自身のプレイング業務を通じて部下に良い影響を与えることで、チーム全体のパフォーマンス向上につなげることができます。例えば、自分の効率的なやり方を部下に見せたり、ともに働きながら部下のコンディションや悩みを把握する、新しいアイディアや方法を一緒に試すなどです。ただのタスク消化・ノルマ遂行ではなく、マネジメント業務実行のための時間に転換してしまう、という発想です。
3.うつべき手段 しかしながら、プレイング比率を30%以下にする、仕事の中身を吟味する、業務改善と部下の教育を兼ねる、どれもわかってはいるけどもなかなかできない、というのが実態ではないでしょうか。そうした難しさを乗り越えるための具体的施策が、以下の3つの手段となります。
1)制度導入・評価制度への落とし込み
プレイングマネジャー の課題を解決するための第一のアプローチは、制度面からの改革です。特に評価制度を見直すことで、マネジャーの行動や意識を変えることが可能になります。
① 単なる部門の結果指標によるKPIではなく、マネジメントがなされているか、組織の成長のための手が打てているかを評価する
多くの企業では、マネジャーの評価は担当部門の売上や利益などの「結果指標」に偏りがちですが、これではプレイング業務に注力せざるを得ない状況を生み出してしまいます。評価制度を見直す際には、以下の点を重視することが重要です。
部下の育成や成長への貢献度
チーム全体の生産性向上への取り組み
プロセス改善やイノベーションの推進
適切な権限委譲と部下の自律性の促進 これらの要素を評価項目に加えることで、マネジャーがマネジメント業務に注力するインセンティブを創出できます。
②単なる評価だけでなく、フィードバックプロセスなどを通じて会社の哲学として伝える
評価制度の改革には、単に評価項目を変更するだけでなく、フィードバックプロセスを充実させることも重要です。定期的な面談や360度評価などの多面的なフィードバック、そして継続的なコーチングを通じて、企業が目指すマネジメントのあり方を「会社の哲学」として浸透させることが効果的です。
特に注目すべきなのは、マネジャー登用前の評価・アセスメント制度の導入です。本人の希望や適性、チームメンバーからのフィードバックなどを総合的に評価し、マネジメント適性を見極めることで、適切な人材をマネジャーに登用できます。また、マネジャーになってからも継続的に多角的な評価を行うことで、マネジメントスキルの向上を促進することが可能です。
2)業務改善によるプロセス再設計
次に重要なのは、業務プロセス自体の見直しです。 プレイングマネジャー の負担を根本から軽減するためには、業務の効率化や再設計が欠かせません。
① そもそも不要な業務をなくす・プロセスを簡素化する
まず取り組むべきなのは、既存の業務フローを徹底的に見直し、不要な業務や重複した作業を排除することです。例えば、定型的な報告書や会議の必要性を再評価し、本当に必要なものだけを残すというアプローチが効果的です。また、自動化できる業務は積極的にITツールなどを活用して省力化を図ることも重要です。
業務プロセスの簡素化には、以下のような具体的な手法が有効です。
業務の棚卸しと必要性の検証
会議の目的と頻度の見直し
報告書やドキュメントの書式と量の簡素化
デジタルツールの活用による業務自動化
② 業務を見直し、部下にできる仕事を改めて洗い出す
プレイングマネジャー が自ら抱え込んでいる業務の中には、実は部下に任せられる仕事も少なくありません。業務を詳細に分析し、以下の視点で整理することが重要です。
各業務に必要なスキルレベルの特定
部下の成長につながる挑戦的な業務の抽出
定型業務と判断業務の切り分け
段階的に権限委譲できる業務の特定 このプロセスを通じて、マネジャーは本来自身が担うべき業務に集中することができるようになります。
③ 工夫をしたりやり方を変えることで部下に任せられる仕事を見出す
一見すると部下に任せるのが難しそうな業務でも、やり方を工夫することで委託可能になるケースがあります。例えば、複雑な業務をいくつかのシンプルなステップに分解したり、チェックリストやマニュアルを整備したり、ペアワークを導入するなどの工夫が考えられます。
効果的な権限委譲のためには、以下のようなアプローチが有効です。
業務の標準化とマニュアル化
部分的・段階的な権限委譲
OJTやメンタリングの充実
失敗を許容する文化の醸成
3)マネジメント研修
最後に、 プレイングマネジャー のスキルとマインドセットを向上させるためのマネジメント研修が重要です。適切な研修を通じて、 プレイングマネジャー は効果的なマネジメント手法を習得し、実践に活かすことができます。
① 部下に任せられる仕事を洗い出し、任せてみるというマネジメント側からのアプローチ
(ア) マインドセットの変革
研修では、以下のような内容が効果的です。
「コントロール」から「信頼」へのパラダイムシフト
マネジャーの役割と責任の再定義
権限委譲のメリットと効果的な方法
コーチングの基本スキル
(イ) 現状に対する気づき
(ウ) 具体的な行動変革の計画策定
② 業務の見える化を行い、業務効率化を実施するという業務プロセス見直し側からのアプローチ
(ア) 業務改善方法の体得
(イ) 業務の見える化
業務棚卸しの方法
プロセスマッピングの技法
タスク分析とボトルネックの特定
業務の可視化ツールの活用
(ウ) 具体的な検討の実施
4.まとめ: プレイングマネジャー を救うためのアクション プレイングマネジャー が直面している課題を解決し、彼らが本来のマネジメント業務に集中できる環境を整えることは、組織の持続的な成長にとって不可欠です。そのためには、以下の3つのアプローチを総合的に実施することが効果的です。
評価制度の改革 業務プロセスの再設計 マネジメント研修の実施
これらの取り組みにより、 プレイングマネジャー のプレイング業務比率を適正な30%以下に抑え、彼らが本来の役割である「チームの成果最大化」と「部下の育成・成長」に注力できる環境を整えることが可能になります。そして、そのような環境が整うことで、「管理職になりたい」と感じる社員が増え、組織の次世代リーダー育成という課題の解決につながるでしょう。 プレイングマネジャーを「救う」ということは、単に彼らの負担を減らすだけでなく、組織全体の生産性向上と人材育成の好循環を生み出すことなのです。成果と育成の両立という課題に正面から向き合い、適切な解決策を講じることで、プレイングマネジャー自身も、組織も、共に成長していくことができるでしょう。
※本コラムの内容に研修実例を交えて、2025/6/16(月)無料オンラインセミナーにて講演 いたします。是非、お申込み、ご視聴ください。
企業研修のことならヒューマンエナジーにご相談ください
ヒューマンエナジーの「カスタマイズ研修」 では、お客様が抱えている課題をお聞きし、目的や組織や人物像を理解して解決案を提示し、個別に研修を組み立てます。カスタマイズ研修には4つの特徴があります。「ビジョン反映型」「社会の変化に対応」「ワークショップ中心」「ゴールまで支援」の4つです。特に 「ゴールまで支援」 の観点から、研修後のフォローアップ施策まで一貫してサポートします。受講者が学んだことを 実務に活かし、確実に行動変容につなげるために、研修設計の段階からフォロー体制を組み込むことを重視しています。具体的には、研修後の事後課題、フォローアップ研修の設計を含めたフォロー施策を提案し、受講者が学びを継続できる環境を整えます。また、単なる知識の習得で終わらせず、「実践し、定着させる」ことを目的としたアクションプランを策定し、職場で活用できる仕組みを構築します。
本ブログの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。
ビジョン反映型カスタマイズ研修
特徴1.ビジョン反映型研修 お客さまの目指す組織・求める人材像を把握した上で、経営ビジョンに沿った研修を実施します。
特徴2.社会の変化・新たなキーワードを取り入れた研修 お客さまのお悩みを伺いながら、VUCA時代に激化する市場競争に対応できる人材と組織を開発します。
特徴3.ワークショップ中心
受講生同士のコミュニケーションを大切にしながら、互いの考えや気づきを共有することで相互理解を促します。
研修の特徴 4. ゴールまで支援
研修後も伴走し、目指す組織・求める人材像に向き合い続けます。
株式会社ヒューマンエナジー 052-541-5650 お急ぎの方はお電話ください(平日9:00~18:00)
この記事を書いた人
代表取締役 神山 晃男 株式会社ヒューマンエナジー ディープリスニングの他、以下のような様々な企業での実務的な経営経験も活かし、経営改善・組織改革から現場の業務効率化まで幅広く、お客様の目的にあわせた研修プログラムをご提供します。<外部役員・他>
本ブログの著作権は執筆担当者名の表示の有無にかかわらず当社に帰属しております。

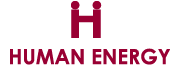





.png)















